感染症防止マニュアル
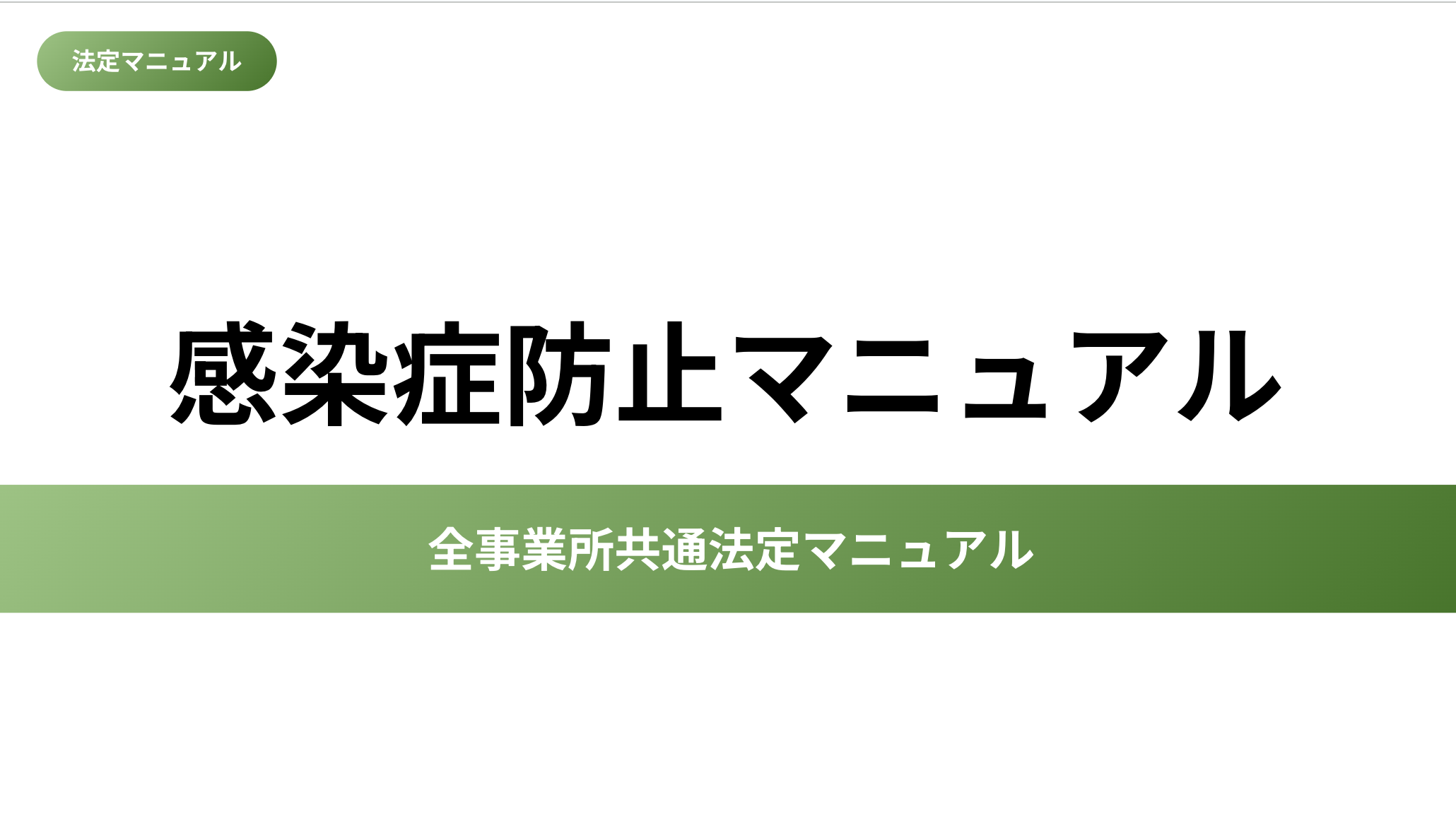
目次
1.マニュアルの主な目的
- 訪問介護を行う際の感染症に関する知識を身に付けることにより、ホームヘルパー等の感染を防止することに繋がります。
- 利用者及び同居家族等が濃厚接触者(同居家族が感染者となり入院した場合を含む)となった場合において、訪問介護サービスが継続できるように、正しい知識と技術を身に付けます。
2.事業所における感染防止の取り組み
- 感染防止に向けて、職員間での情報共有を密にし、職員が連携して感染防止対策に取り組みます。
- 感染者発生時に円滑に疫学調査に協力できるよう、利用者のケア記録(体温や症状など)と直近2週間の勤務記録を準備しておきます。
- 入国拒否対象地域から帰国後に症状がある職員がいる場合、施設長は速やかに市区町村に人数、症状、対応状況を報告し、感染が疑われる場合は保健所に報告して指示を求めます。また、最新情報を収集し職員に提供してください。
3.職員の感染防止における取り組み
- 職員、利用者、委託業者など接触の可能性がある全員がマスク着用や咳エチケット、手洗い、アルコール消毒などで感染経路を断つことが重要であります。
- 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」などを参照し、対策を徹底します。
- 職員は出勤前に体温を計測し、発熱などの症状がある場合は出勤を控えてください。発熱があった場合は、解熱後24時間以上経過し、咳などの呼吸器症状が改善するまで同様に扱います。状況が改善しても健康状態に注意し、該当する職員は管理者に報告して確実に把握してください。
※ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等含むものとします。 - 発熱や呼吸器症状で感染が疑われる職員については、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に基づいて適切に対応してください。
- 職場内外で感染拡大を防ぐためには、換気の改善や密集を避ける対策を徹底することが重要であります。
- 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接する際にはマスクを着用してください。
4.ケア等実施にあたっての取り組み
サービス提供の際は、事前に利用者本人や家族、職員が体温を計測し(可能であれば事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が確認された場合は「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に基づき適切な相談と受診を行うよう促してください。
また、サービス提供に際して以下の点に留意してください。
5.感染者が出た時の対応について
6.感染症対策委員会について
- 感染症の予防と拡大防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6カ月に1回以上開催し、その結果を職員に周知徹底させること(委員会はテレビ電話などの情報通信機器を活用して行うことができる)。
- 事業所における感染症の予防と拡大防止のための指針を整備すること。
- 職員に対し、感染症の予防と拡大防止のための研修や訓練を定期的に実施すること。
| 対策内容 | 頻度 | 備考 |
|---|---|---|
| 感染症予防・拡大防止対策の委員会開催 | おおむね6カ月に1回以上 | テレビ電話等の情報通信機器の活用が可能 |
| 事業所における感染症予防・拡大防止の指針整備 | 必要に応じて | |
| 職員に対する感染症予防・拡大防止の研修・訓練 | 定期的に(頻度は事業所による) |

